壱章・始まり
ばたん。
ドアが乱暴に閉められる音は嫌に耳に付くが櫻子は今日の朝もその音で目を覚ました。
その音を立てているのは、櫻子の隣の家に住む高校生で現在反抗期の須田武志だ。
武志は近くに同学年の子供がいなかった櫻子のいい遊び相手で、櫻子も武志を「お兄ちゃん」と呼び慕っていた。だが、最近武志は櫻子に冷たくなり、櫻子が何か話しかけても返すのは「うるさい」の一言。外にもあまり出ようとしないが、かといって出かければ家に帰って来る時間が夜十時近くになることも増えていた。
しかし、櫻子は十歳になりながらも家の近くに武志以外の遊び相手がいない。
だから今まで両親の許可無しに勝手に家を飛び出すことなど無かったとはいえ、この日、櫻子が武志が家を出ていく音を聞きつけ、こっそり跡をつけることにしたのには何ら不思議はなかった。
武志が後をつける櫻子にも気づかずに、憑かれたかのようにまっすぐに向かった先は、家からそう遠くない神社だった。
――こんなところで何を?
そう思いながらも、櫻子は武志を見失わないよう懸命にあとをつける。
武志は神社の森に入り、その森の奥へ奥へと進んでいく。そして二十分ほと経っただろうか。武志はその神社の森の中にある御神木の前まで来てやっと立ち止まったかと思うと、突然苦しみはじめ、膝から崩れ落ちた。
「お兄ちゃん!」
櫻子は思わず、倒れた武志に駆け寄る。
すると、苦しそうに喘ぐ武志の陰に、何かが蠢いているのが見えた。
その何かは武志の陰の中で動き、波打ち、そして不意にぐにゃりと盛り上がって人の形をとり、櫻子を、見た。
櫻子の背中に、今までに感じたことのないような悪寒が走り抜ける。
「ナンダヨオマエ……?サッキカラツイテキヤガッテ!トリツイテヤルゾ!」
逃げる暇も叫ぶ暇もない。櫻子は次の瞬間には、その陰から生まれた何かに首を締め上げられていた。それの手はぬめりを帯び、てらてらと気色の悪い光沢を放っている。柔らかそうに見えるその手は、それでいて容赦なく櫻子の呼吸を困難にした。
――と、その時、突然櫻子はそれの手から解放された。というより、それが突然消えていた。
櫻子が眼を開けてみると、櫻子自身の身体が何かベールのようなものに包まれて光っており、人の形をした陰はすうっと消えていくのが見えた。まばゆい光に目が眩む。
そして、気がつくと辺りにはなんの気配も無く、武志が一人、倒れているだけだった。
「驚きましたか?」
櫻子は誰かの声ではっと我に返り、その声の方向を振り向いてみると、銀髪の青年が立っていた。
「今、あなたの身体が光ってお化けが消えたでしょう。それはあなたの持つ特殊な能力なんです」
その青年は一色凜と名乗り、薄く笑いながら、櫻子が全てを浄化するという力を持った特別な存在であることを簡単に説明した。
「よく……分かんないよ……」
櫻子が困惑していると、凜はまた笑う。
「今はまだそれで結構です。それより早くお兄さんを運びましょう」
突然現れた見知らぬ青年が、特に何も言わず武志を運ぶと言い出したことに、櫻子は何の疑問を持たなかったわけではないが、細身な割に武志を軽々と持ち上げ早くも運び始めた凜のあまりの手際のよさに、櫻子はただただ目を丸くして凜の後を追うしかなかった。
彼は走っていた。走って逃げていた。
逃げながら彼は考える。
何故、こんなことになってしまったのだろうか。
つい昨日までは、兄の様子はいつも通りだった。
それなのに、兄の猫が兄に何か伝えてから、兄は突然力を暴走させ始めたのだった。
彼は兄が猫に何を聞いたのかは分からないが、猫が兄に伝えたことは一言だった。
それだけのことだが、そのことからも彼には想像がつく。
おそらく、彼の兄が力を暴走させ始めた理由はこうだ。
――兄が最も憎んでいる人物、双子の兄が長い眠りからさめたことを聞いてしまったのだ。
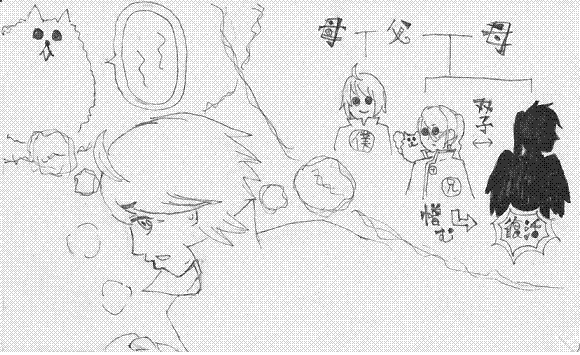
 Home
Home First
First ロン毛ライダー
ロン毛ライダー Link
Link Index
Index